|
|
|
 |
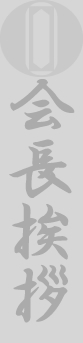
 |
  |
 |
|
 |
 |
 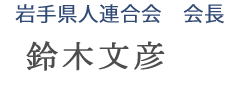  |
 |
ご挨拶
さあ、元号が改まっての令和元年の「岩手県人の集い」であります。これまで以上にふるさとを愛する同志の集まりを目指したいと願っております。
齢を重ねればいろいろな体験があるものです。“禍転じて福と成す”現象がたびたび起きます。もちろんその逆も同量あるのですが、そこはそれ、万事よい方に発想を転じまして———。
昨年師走のこと、帰省しようとして新幹線に乗り遅れました。で駅で問うたところ、16分後の「やまびこ」自由席なら切符を買い直さずに行けるとのこと。急ぐ旅でもなし、弁当を求めて乗りこんだところ、これが快適。隣りは空席のまま読書三昧の至福の時間でした。以降、やまびこ愛好者になっています。
また先日、「奇想の系譜展」を鑑賞したときのこと。若冲、又兵衛、蕭白などに白隠、鈴木其一を加えた八人の江戸絵画展が混雑必至といわれたのですが、土曜日閉館間際の六時半に行ったところ大正解。たっぷり観ることができました。(この時間お薦めです)
半世紀前に美術史家・辻惟雄氏が称えた「奇想の系譜」がいまの日本美術ブームを生んだといっても過言ではないのですが、この奇の精神に目を見張りました。美術の世界では、伝統の型から入って型を抜けるのを旨とし、「型破り」が創造の核となるというのです。その自由さを求めて絵画展に行っていたのだと気付かされた次第です。
絵についてもう一つ。
「絵を描くことが好きで、ここまできた。でもこのところ、本当に描きたいものが自分の中にあるんじゃないかと思い始めた。それを探すためにこれまで、毎日描いてきたんじゃないかと。だからその描きたいものが何かを暴いて、皆さんに示したい」
これは文化勲章受章者で98歳の画家・野見山暁治さんの最近の弁です。煙に巻くともおとぼけとも見えるこの味は、なかなかに年齢を重ねないと出てこない。実力と芸が必要です。
ですが、何事も経済優先に進む世の中、余裕や遊びを失いつつある昨今において、「おとぼけの効用」は意外に貴重かもしれません。
決して正義ぶらず、常識に捉らわれず、重々しくならず———この線で六月二日にお目にかかろう、と思っています。
岩手県人連合会 会長
鈴木文彦
|
 |
|
|
|
|
| Copyright(c) IWATE KENJIN RENGOKAI All Rights Reserved. |
|
|